Masaki Kawada Web
- オールド/ニュー準備室 vol.7
オールド/ニュー準備室 vol.7
僕の作品の中に「一冊の栞」という作品があります。
この作品は、一冊の本(主に文庫本)のページに絵を描いたり、メモを施したり、写真を挟んだりしたものになるのですが、どうやら、このような作品に少なからず抵抗を憶える方がいるようです。
理由はといえば「愛着のある本に絵を描いたり、時にはページを切り取ってしまうという行為に対して、そんなことはできない」ということになるのですが、僕もそのような意見にまったく同意できないというわけではありません。
僕の中にも同様に、本にそのようなことを施してしまうことに、そして「一冊の栞」として作品化することに抵抗を感じる時があるからです。
けれども、本の捉え方、考え方によってはそのようなことがあまり重要なことではなくなる時があります。
それは、小説(文学)にとって本という形式、形体はその空間を見えるものにするためのひとつの手段、方法でしかなく、むしろ、それらを無視したものとして見ようとする、言い換えれば、本来、小説の持っている空間、文学空間がより重要なこととしてあるという見方をするときです。 (しかしながら、それは何かしらに寄り添うことで僕たちは見ることができるのですが。)
そのような考え方、捉え方は「アートする美術」にも反映されていることでもあります。
確かに、新書という形式、形体は重要なことではあるのですが、しかし、ページに印刷された文章、言葉にとっては、そのような形式、形体は数あるうちのひとつの形式、形体でしかなく、必要があれば、本という形式、形体を無視することもできるのです。(もちろんその場合には、その形式、形体に対して再考、再編集する必要があります。そして、そこが重要なことでもあります。この事についてはいずれお話できればと思います。)
「一冊の栞」の場合も、本というものを、白紙のページが束になったものに印刷によって言葉が描かれものと捉え、僕はそのような現われに身を委ね、時には無視しながら、その小説(文学)のもつ空間に、そして本という空間に寄り添っていくことになります。
しかしながら、当然のように作品を制作する過程においては、そのような考えも変更、修正、そして無視することさえ必要な場面に出会うことも多々あり、あくまでここで書き連ねた言葉、考えも、どこまでも仮の、小説の現われ同様に、ひとつの現われでしかないのでしょう。
そして、付け加えるなら、作り手である作家が語る言葉が時に真実であり、時に偽り、はぐらかしである所以はそこにあるように思われます。
2002年9月13日(金)




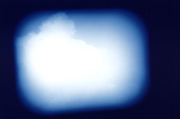
『オールド/ニュー準備室 2002年9月21日号 vol.7』 / かわだ新書プロジェクトホームページ / 2002年